
デジタル化以前のフィルム時代から、写真撮影にいそしんでいる人なら、昔のカメラ操作の手応えと期待感を覚えていることでしょう。
それを今、デジタルカメラで体感することができる、富士フィルムのコンパクトカメラが登場しました。
その名前はX-half(X-HF1)。
このカメラはフィルム撮影の楽しさ(ある意味不便さ)を、デジタルで再現させることを目的に設計されています。
今回はX-halfの魅力をじっくり掘り下げ、撮影体験がどう変わるのか、ユーザーレビューを交えて検証してみたいと思います。
X-halfの特徴 ー “ハーフサイズ” が映える設計になっている
 FUJICA Half 参照:ALMAYAR.NET
FUJICA Half 参照:ALMAYAR.NET
X-halfは、35㎜フィルムハーフ版カメラをデジタルで再構築させたモデルで、かつて富士フィルムにもあった「FUJICA Half」シリーズがモチーフになっています。
搭載するセンサーは高級コンパクトに多い1インチの、1778万画素のものを採用し、アスペクト比は3:4の縦長としています。
 参照:価格.com マガジン
参照:価格.com マガジン
ファインダーはEVFではなく縦長の光学ファインダーで、同様に液晶モニターも縦長と、縦位置を標準とするカメラ設計です。
この組み合わせによるインターフェイスで、縦構図撮影が自然に身に付く点が魅力となっています。
と言っても普段スマホで撮影する人なら、何の抵抗もなく馴染むことでしょうね。

そして撮影時にフィルムカメラモードを選べば、アナログ的な撮影感を盛り上げるフレーム切り替えレバー(フィルムカメラで言うフィルム巻き上げレバー)を操作することで、撮影が楽しくなるんです。
つまり、1枚撮るごとにレバーを引いて次の撮影へ移る、フィルムカメラのような一連の流れが体験できるんですね。
X-halfはコンパクトかつ高品質なボディデザインだ

本機の質量は、バッテリーとSDカード込みでわずか約240g。
手のひらサイズの大きさは、携帯カメラとして申し分なく、撮ろうとしたらすぐに構えられる感覚です。

ボディは軽いだけに全体がプラスチック製になっていますが、デザインはクラシックカメラの品格をまとい、角が丸みを帯びたグリップ側と刻印文字など、丁寧な仕立てが感じられるものになっています。
設定操作は最新のデジカメだけあり、液晶モニターはスワイプ・フリック対応のタッチパネル方式で、滑らかなユーザーインターフェースです。
X-halfは撮影表現を楽しむ機能でいっぱい

●「フィルムモード」でアナログ的緊張感と出来上がりを待つ楽しさ
本機で最も楽しい使い方ができるのがこれ。
まずはメーカーの動画で、このモードのイメージを掴んでいただきましょう。
前もって撮影枚数を設定し(36枚/54枚/72枚)、液晶モニターを見ずに光学ファインダーのみで撮影します。
設定した枚数を撮り切るまで、写真の確認はできません。
撮影後専用アプリでデジタル現像(実際に現像する訳ではなく雰囲気を演出)、その後に結果を見ることでドキドキ感が味わえます。
アプリ上ではコンタクトシートが自動的に生成され、楽しく見比べられます。

●「2-in-1」機能で2枚1組の組み写真を簡単に作ることが可能
1枚撮影後、フレーム切り替えレバーを引いて次の1枚を撮影します。
縦構図の2枚を組み合わせて、1枚の画像として保存ができるんです。
これは静止画同士に限らず、静止画+動画、動画+動画と言った組み合わせにも対応。
専用アプリ使えば、真ん中を分割する線の色変更や左右の入れ替えも自由に行え、ストーリーを作る楽しさも深まるでしょう。

●多彩な色調・質感表現が楽しめるフィルター群が揃っている
Xシリーズでおなじみのフィルムシミュレーションは、PROVIA・VELVIA・REARA ACEなど13種類を用意しています。
これらは、液晶モニター左側のサブ液晶で設定します。
また、新開発のライトリーク・ハレーション・期限切れフィルムの3種類に加え、チェキのようなinstaxの8種類のフィルターも収録し、トイカメラ風の表現を行えます。
さらに、粒状感をデジタルで表現するブレイン・エフェクトを使えば、画面にフィルム調の画像処理を加えることも可能です。
さらにフィルム写真時代にあった、ノスタルジックな日付入り撮影機能も搭載。
X-halfは堅実な描写力を持ったスペックだ

先に少し述べましたが、本機のセンサーは1.0インチ裏面照射型CMOSで、総画素数は1.774万画素と描写する質感は十分高いです。
ただし、ファイルはJPEGのみでRAWは不可能となっており、画質そのものより撮る楽しさを追求したカメラになっています。
レンズは35㎜判換算で、約32㎜ F2.8の単焦点。
これは、「写ルンです」と同等の画角に合わせたと言うことです。

フィルム時代のカメラのように、レンズ胴鏡にフォーカスリングと絞りリングを搭載して、MFで操作することの楽しさを味わうことができます。
AFももちろん可能で、9点のフォーカスポイントが備わっています。
ただし、光学ファインダーは先述の通り素通しファインダーなので、フォーカスポイントを確認することはできません。
基本的に “写真を撮る” ことを優先したモデルなので、動画性能はほどほどのもの。
4Kはなく、最大でフルHDとなっています。
バッテリー寿命は、全てファインダーを使った場合で約880枚と、じっくり撮るなら十分な性能と言えるでしょう。
X-halfのユーザーレビュー
では、X-halfを実際に使っているユーザーの皆さんは、本機にどんな感想を抱いているのでしょうか?
いくつかユーザーレビューをピックアップしたので、ここでご覧になって下さい。
★「X-halfを正直に表すなら “写ルンです的な気軽さx富士フィルムの味x遊び心” 。写真の “写り” を追求するというより “撮る行為そのものが楽しい!” を体現したカメラだ。否定的にいえば、AFは速くないしRAWは非対応。画質もスマホ並み?ただし、それすらもこのカメラの “気軽に楽しむ” という文脈では許容範囲だ。だが撮影体験という点では話が別。巻き上げレバー風の操作感や縦位置センサーによる画面構成の新鮮さ、富士フィルムらしい色再現はとても魅力的。JPEG直出しで、ここまで “楽しい絵” が得られるカメラはなかなかない。」
★「X-halfのシルバーを購入した。レトロ調カメラはいつもシルバーを選んでいて、革製のストラップやカメラケースでデコレートしたいと思っているので、相性の良いシルバーがベストだ。実物を手にしてみるとシルバーの質感は思ったより上質で、落ち着いた色合いだ。ハーフサイズのフィルムカメラを、デジタルで再現するというコンセプトに惹かれて購入したが、実際に手元に届いてみて事前の不安は払拭され、満足のいく一台となった。」
★「綺麗に写って高性能!なカメラを求める人は、このカメラを買ってはいけない。このカメラはノスタルジーを感じつつ、写ルンです的な使い方を楽しむカメラだ。機能的には、静止画・動画どちらも撮れる。手ぶれ補正機能はなし。ファインダーは、ハーフカメラらしい縦構図だ。液晶も3:4。ガラス素通しで、何の機能もなく視度調節もないので、撮影時にピントの状況が全くわからない。そのためMF時に苦労する。液晶に小さく表示される距離表示が頼りだ。MFアシストとして合焦面を白などで表示できる。起動は遅く、オンから撮影可能まで1秒以上かかるので、咄嗟のスナップは難しい。ほんとに30年~40年前のカメラのテンポでの撮影になる。」
★「賛否両論あるカメラだが刺さる人は刺さる。デジタルフィルムカメラ、もしくはデジタル写ルンですという表現がいいのかも知れない。普通のコンデジを期待するなら違うカメラを買えば良いと思う。そういうのを期待する人は、GRを買った方が良いだろう。」
参照:価格.com Amazon
まとめ

今回のX-halfは簡単に言えば、コンパクトなボディにとことん高性能を追求したものではなく、コンパクトさの中に、レトロな機能をギュッと詰め込んだカメラなのは明白です。
現在発売されているミラーレスカメラ・一眼レフカメラは、多彩な機能や高度な性能を突き詰めたものが多いですよね?
それはそれで良いのですが、反面、ボディが重かったり使わない機能が多すぎと言ったデメリットも持っています。
一方、昔のカメラは機能・性能はほどほどだったものの、機械を操る(あやつる)と言う点でそれが楽しくもありました。
このような要素を、わざわざ現代のデジタル技術で再現したのが本機でしょう。

しかし、ただ昔を再現しただけでは、単にデジタルトイカメラになってしまいます。
そのため本体の軽量化とともに、仕上げの良さを前面に押し出した造りになっている訳ですね。
よってこのカメラを購入するターゲットは、ズバリ、カメラを知り尽くしたベテランユーザーです。
昔を知らず、スマホカメラしかいじったことがないユーザーでは、本機の良さを理解するのは難しいのではないでしょうか?
あらゆる機能を持った本機ではありますが、これは写真撮影に特化したもので、動画に関しては一応撮影はできるものの、性能は平凡。
4K撮影はできないし、32㎜の画角は望遠寄りで使いにくいものです。
総合的に見ると、操作することに喜びを感じる人にはとても魅力的な商品ですが、ただ価格的には少々高過ぎと言う感はします。
私の感覚では、適正価格は7万円から8万円。
でなくても、せめて10万円を切る設定にすべきではなかったか?
そんな訳で、X-halfは少々お小遣いに余裕のあるカメラ上級者にピッタリのアソビカメラ、と位置付けしておきましょう。
![]()
または
![]()

メーカーサイト:富士フィルム


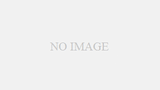
コメント